「注文住宅って、思った以上にお金がかかる…」
家づくりを始めた多くの方が、最初に直面するのがこの現実です。
・「住宅ローン、いくらまで借りられるんだろう」
・「今の収入で、本当に家が建てられるのかな?」
そうした不安を抱えたまま進めてしまい、予想外の出費に直面して、「最初にもっと資金計画を立てておけばよかった」と後悔する方は少なくありません。
ですが、正しい知識と手順があれば、予算オーバーのリスクは防ぐことができます。
この記事では、住宅営業として数多くの家づくりを見てきた経験をもとに、
を、初心者の方にもわかりやすく解説します。
この記事を通して、お金の不安を解消し、予算オーバーを防ぐ家づくりの第一歩を踏み出しましょう。
よくある失敗例から学ぶ「資金計画の落とし穴」
注文住宅で後悔する人の多くは、「ちゃんと考えたつもりだったのに…」というケースがほとんどです。
では、どこでつまずいてしまうのか?
まずはよくある失敗例から、資金計画の落とし穴を見ていきましょう。
予算オーバーの実例(外構・家具・オプション追加など)
注文住宅を建てた方の多くが口を揃えて言うのが、「思ったよりお金がかかった」という後悔です。
たとえば──
- 本体工事費は契約時の想定通りだったのに、オプションの追加で+150万円
- 家具・家電をすべて新調したら、引き渡し後に一気に+100万円以上の出費
- 外構費用やカーポートを後回しにしていたが、見積もりを見て驚愕。「今の予算じゃ無理…」
こうした“後から追加される費用”は見落としやすく、最初にざっくりとした金額だけで動いてしまうと、後戻りができません。
特に注文住宅は、選択肢が多い分、「せっかくなら…」の積み重ねで予算が膨らみがち。
この予算オーバーの連鎖を止めるには、最初の段階で全体像を把握しておくことが何より重要です。
“借りられる額”と“安心して返せる額”は別物!
注文住宅の資金計画でよくあるのが、「住宅ローンが通ったから大丈夫だと思った」という誤解です。
たしかにローン審査に通るということは、「借りられる金額」はクリアしているということ。
でも、それはあくまで
“返済できる能力がある”というだけで、“安心して暮らせる”とは限りません。
よくあるのが、こんなケースです👇
こうした“余裕のない暮らし”になってしまえば、せっかく建てたマイホームの満足感も薄れてしまいます。
だからこそ大切なのは
💡 「借りられる額」ではなく、「暮らしにゆとりを残せる額」で考えること。

「月々いくらなら生活に余裕があるか?」
まずは家計の収支を整理して、“ゆとりのあるライン”を見つけることから始めてみよう!
まずやるべきは「わが家の予算の把握」
家づくりでまず最初に取り組むべきなのが、「わが家の予算を知ること」です。
いくらの家が建てられるか?ではなく、「いくらなら無理なく返していけるか」を知ること。
それが、予算オーバーを防ぐ最も確実な方法です。
このパートでは、
について、初心者でもわかるように解説していきます。
総予算の出し方(年収、自己資金、支出見直し)
注文住宅の総予算は、「いくらまで出せるか」ではなく、
「どこまで出しても安心して暮らしていけるか」で考えることが重要です。
まずは、ざっくりでも構いません。次の3つを整理してみましょう👇

「今払える」じゃなくて、「払っても笑って暮らせる」が理想のライン。
まずは家計簿アプリで、1か月のリアルな支出を“見える化”してみよう!
月々返済額の目安
資金計画のカギは、「今だけでなく将来も見据えた、無理のない月々返済額」を把握することです。
住宅ローン審査で“借りられる額”が分かっても、それをそのまま使い切るのはキケン⚠️
📌 無理のない返済額は、家計にゆとりが残るラインを基準に考えるのがポイントです。
よく言われる目安は「手取り月収の20〜22%以内」ですが、各家庭の固定費やライフスタイルは異なります。
一律の基準にとらわれず、“自分たちの家計”に合わせて調整することが大切です。
特に住宅ローンの金利タイプによって、月々の返済額やリスクは大きく変わります。
👉 固定金利と変動金利、どっちがいいのか迷っている方は必見!
将来後悔しないための金利タイプの選び方は【初心者向け】住宅ローン固定金利vs変動金利どっちがいい?にまとめています👇
金利の選び方に悩んでいる方は、先にそちらを読んでからでもOKです。
そしてもう一つ忘れてはいけないのが、「将来の大きな支出」に備える視点です。
こうした将来の支出を考慮して、“余白”のある返済計画を意識することが、長く安心して暮らすコツです。

ボーナス払いを前提にすると、収入が減ったときに返済が苦しくなりがち。
収入が減ったときに破綻しやすく、結果的に“無理のある計画”になってしまうことが多いからです。
月々の支払いだけで成り立つプランを基本に考えて、無理なく返せる仕組みを整えていきましょう!
家づくり全体から逆算して建物予算を決めよう
「どんな間取りにしようかな」
「このキッチン、憧れだったんだよね」
夢がふくらむ家づくりですが──
その前に立ち止まって考えたいのが、“全体の予算バランス”。
というのも、注文住宅では建物以外にも想像以上に費用がかかるからです。
土地代、外構、登記や火災保険、家具・引っ越し代…
それらを含めて初めて「本当の家づくりのコスト」が見えてきます。
そこで大切なのが、
“家づくり全体の予算”から逆算して、建物に使える金額を見極めるという考え方。
無料で間取り・見積もり・土地提案まで比較できる便利なサービスもあるので、
「うちは建物にいくら使えるか?」を可視化するのに活用してみるのもおすすめです👇
無料で間取り作成!? 【最新版】タウンライフ家づくり5つのメリット|口コミ&評判まとめ
この章では、予算オーバーを防ぐために欠かせない“逆算の視点”と、注意すべき落とし穴について解説します。
“住宅ローンの限界=建築費”じゃない!
間取りや仕様を決めていくうちに、営業担当から
「このオプションは人気ですよ」
「このグレードの方が後悔しませんよ」
と提案が続き、気づけば“借入可能額ギリギリ”の見積もりに…。
でも──ちょっと待ってください。
住宅にかかる費用は、建物代だけじゃありません。
土地代や外構、登記・保険などの諸費用、そして引っ越し・家具代まで…
“家づくりの総額”を見ないまま建物予算だけを膨らませるのは、危険です。
📌 家づくりに必要な費用の全体像👇

建物に全力投球した結果、外構が手つかずで砂利のまま…
そんなケースもあります、、、
だからこそ大事なのは、“建物だけ”ではなく“家づくり全体”の費用から逆算して建築費を決めること。
住宅ローンの限度額=建築費、ではありません。
家づくり全体にかかる費用を把握し、その上で“建物にいくら使うか”を逆算することが大切です。
建物以外にかかる費用の一覧と具体例
「建物本体に〇〇万円かけられますよ」と言われると、ついその金額でプランを組みたくなってしまいます。
でもちょっと待ってください。
家づくりにかかるのは、建物代だけではありません。
さきほど触れたように、外構や諸費用、引っ越し代や家具家電…
実際は“建物以外”の費用も想像以上にかかるんです。

「予算ギリギリで契約したら、後から外構が別って言われてパニック!」
これ、リアルにある話です…
これらの費用項目の中身や金額の目安、後悔しやすいポイントについては、こちらの記事でくわしく解説しています👇️
注文住宅の予算オーバーはこう防ぐ!費用の内訳で見直す【5つの賢い選択】
見積書を見るときの注意ポイント
「これくらいの金額なら大丈夫そうだし、あとは間取りを詰めていけばいいかな」
──そう思ったそのとき、少しだけ立ち止まって見直してみてください。
注文住宅の見積書は、“本体価格だけ”が記載されていることが多く、あとから【外構・登記・火災保険など】の追加費用がかかるケースも少なくありません。
つまり、今見ている見積もりは、家づくり全体のうち“建物部分だけ”を示したものかもしれないんです。
外構や諸費用が抜けていると、**総額を正しく把握できず、後で予算オーバーに…**というリスクも。
📌 大切なのは、「この見積もりに“含まれていない費用”はないか?」という視点を持つこと。
この章では、見積書を見るときに注意したい落とし穴と、比較検討するときに見るべき“本当の総額”についてわかりやすく解説します。
「建物価格だけ」で判断するな!
見積書を見たときに「おっ、意外と安いかも?」
──そう思ったこと、ありませんか?
でもちょっと冷静になって見直してみてください。
その金額、本当に「全部込み」の見積もりですか?
実は、注文住宅の初回見積もりでは“建物本体価格だけ”が提示されているケースが多いんです。
📌 住宅の見積書に含まれる代表的な費用構成
しかし実際には、
- 地盤改良や上下水道の引き込み費用
- 外構(駐車場・フェンス・庭)
- 登記・印紙・火災保険などの諸費用
- 家具家電や引っ越し代、仮住まいの費用
といった“建物以外”の費用が別でかかります。

「あとから“これは別途です”って言われたときのショック、でかいよ…」
本体価格だけで安心してたら、トータルで数百万円単位のズレになることも!
だからこそ大事なのは、
👉 「総額ベースで見積もりをチェックする」という考え方。
このあとの章では、他社比較のコツや“数字の見せ方”に潜む落とし穴についても解説していくよ!
全体の見積もりに“漏れ”がないか確認するクセをつける
「これくらいなら予算内におさまりそう」
──そう思っていたはずなのに、最終段階で
「えっ、こんな費用も必要なの?」と驚く人は少なくありません。
その原因は、見積書に“建物以外の費用”が反映されていなかったから。
💡 たとえば、以下のような項目が“別途”扱いになっていないか、必ずチェックしましょう👇
📌 大切なのは、「この見積もりで本当に“全部入っている”のか?」という視点を持つこと。
営業担当が最初に出す見積もりは“最低限プラン”になっていることも多いため、追加費用の可能性については早めに確認し、見落としがないかを自分でもチェックするクセをつけましょう。
よくある質問とその回答
- Q1他の借入れがある場合、住宅ローン審査にどう影響しますか?
- A
他の借入れがある場合、その返済額が審査の際に考慮されます。総返済負担率(年間返済額の総額が年収に対する割合)が高すぎると、審査に通りにくくなります。可能であれば、他の借入れを完済しておくことが望ましいです。
- Q2住宅ローン審査において、最も重要なポイントは何ですか?
- A
住宅ローン審査において最も重要なポイントは、返済能力です。銀行や金融機関は、申込者が毎月の返済を無理なく行えるかどうかを重視します。収入、雇用形態、勤続年数、他の借入状況などが評価されます。
- Q3住宅ローンの借入額を決める際の目安はありますか?
- A
住宅ローンの借入額は、通常、年収の5~7倍を目安とすることが一般的です。ただし、返済能力を超えないようにし、無理のない範囲で設定することが重要です。月々の返済額は、家計収支を考慮して収入の20~22%程度に抑えるのが理想です。
- Q4資金計画で注意すべきリスクは何ですか?
- A
資金計画において注意すべきリスクには以下があります。
- 金利上昇リスク: 変動金利を選んだ場合、金利上昇によって返済額が増加するリスク。
- 収入減少リスク: 失業や病気などで収入が減少した場合のリスク。
- 予期せぬ支出リスク: 修繕費や医療費など、突発的な大きな支出が発生するリスク。
まとめ:資金計画の“見える化”が、後悔しない家づくりの第一歩!
「注文住宅って、こんなにお金がかかるの⁉」
──そんな声が出るのは、たいてい“最初の見積もり”や“資金計画”に見落としがあったからです。
ですが、
✅ 正しい順序で進めて
✅ 必要な費用を把握し
✅ ゆとりのある返済計画を立てれば、
予算オーバーは防げます。
📌 この記事で押さえておきたいポイントをもう一度おさらい👇

「建てることがゴール」ではなく、
家を建てたあとも、外食や旅行、子どもの教育費に“余裕をもって使えるか”を意識しましょう。
どんぶり勘定で進めてしまうと、あとからツケが回ってきます。
だからこそ、「お金の見える化」から家づくりを始めましょう。
安心して住み続けられるマイホームを手に入れるために──今、できる準備から始めよう!
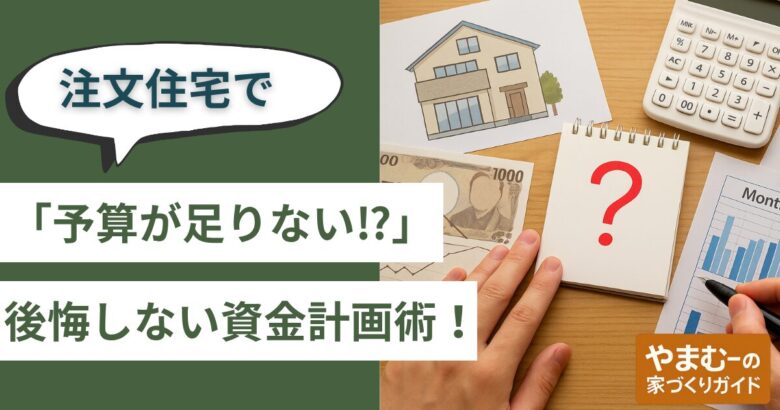

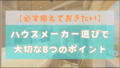
コメント